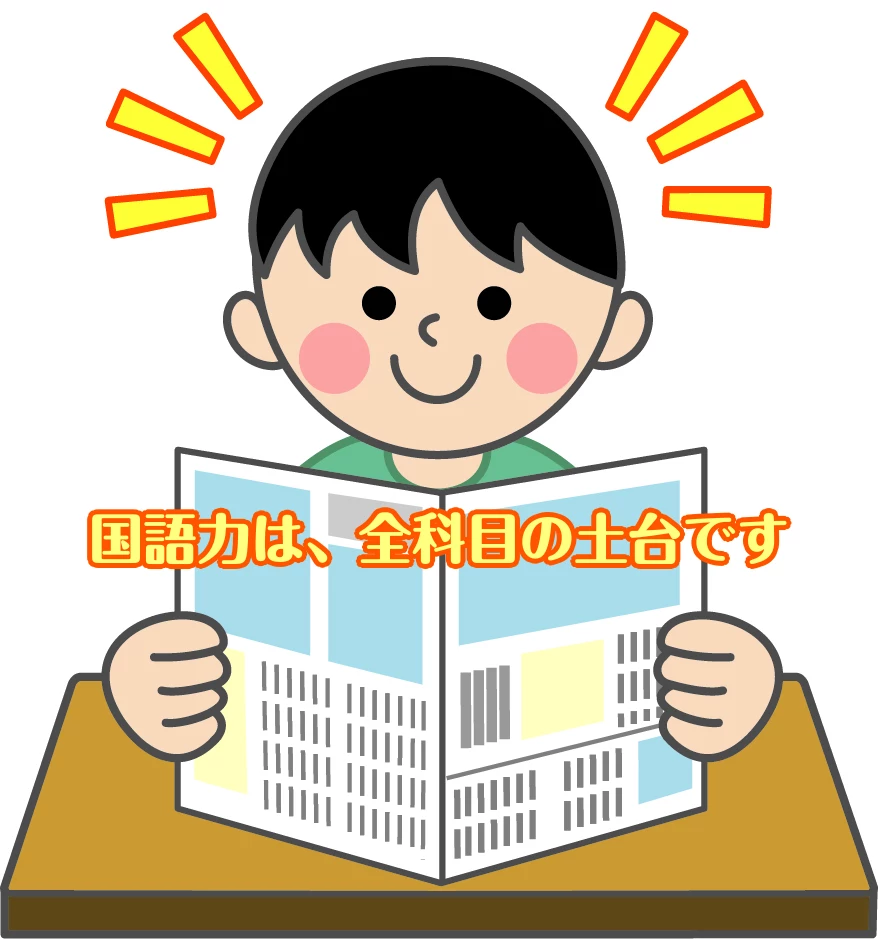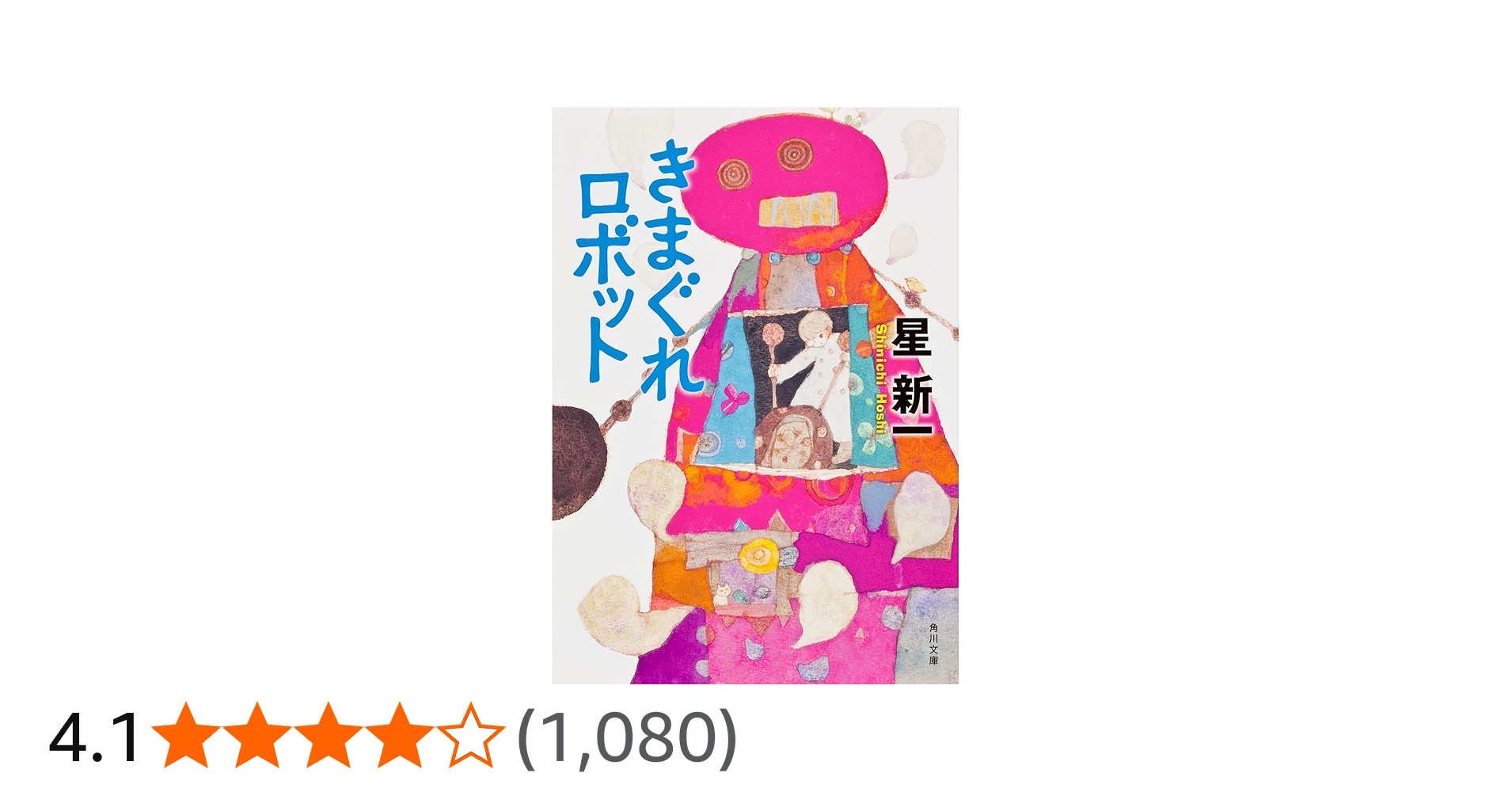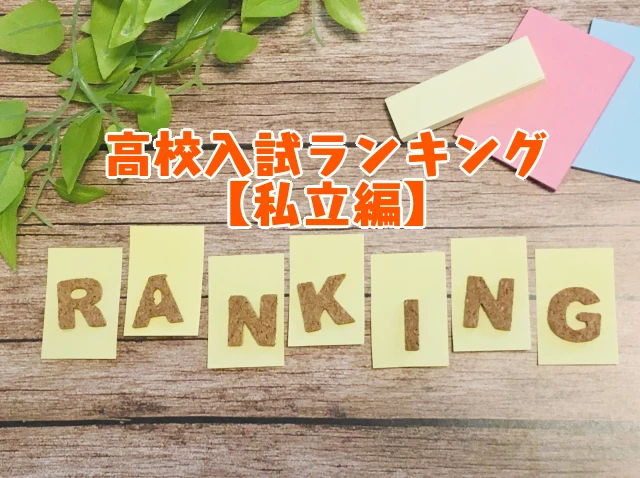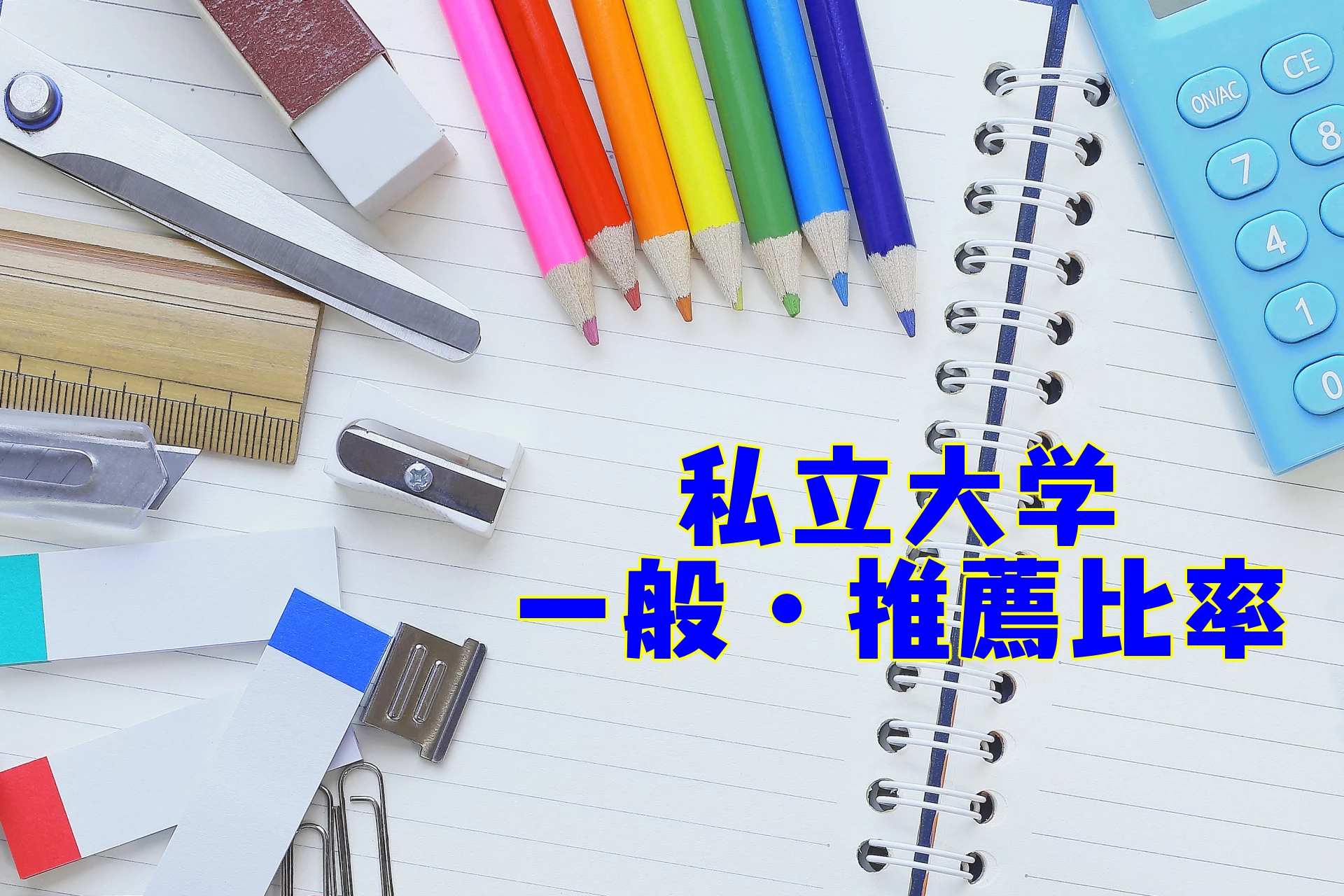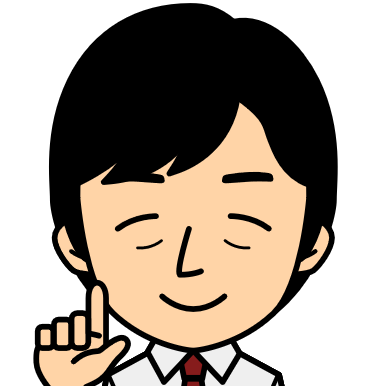
個別指導ひとすじ29年、名学館の加藤と申します。
今回は、国語という科目の重要性についてブログを書きました!
あとまわしにされがちな“国語”ですが、実はすべての学力の根底にあるのが「国語力」です。
国語力は、学力を動かす“エンジン”のようなもの。
読む力・考える力・表現する力が備わることで、英語も数学も理科も社会も、理解の深さがまったく変わってきます。
目に見えにくい力ですが、ここを育てることが、学びの質を大きく変える第一歩です。
偉人たちが語る「国語力の大切さ」
まず、『国家の品格』(200万部を超える大ベストセラー)の著者である 藤原正彦先生(お茶の水女子大学名誉教授) は、著書の中でこう述べています。
ちなみに、藤原先生は数学者です。
数学者であるにも関わらず、算数よりも国語教育の重要性を説いています。
また、数多くの著書をもつ 樋口裕一先生(多摩大学教授) は、こう述べています。
さらに、『AI vs 教科書が読めない子どもたち』の著者 新井紀子さん は、こう述べています。
新井さんも数学者です。
数学者でさえこう言い切るほど、国語力の影響は計り知れないのです。
国語力が、他教科の学びを加速させる
実際に中学生の塾生を見ていても、成績上位層の中で国語が苦手な子は少数です。
国語力が全科目の下支えとなり、読む・考える・解くスピードが速いのが特徴です。
私の指導経験から申し上げると、例えば、算数の文章題が苦手な生徒は、国語が苦手なケースが非常に多いです。
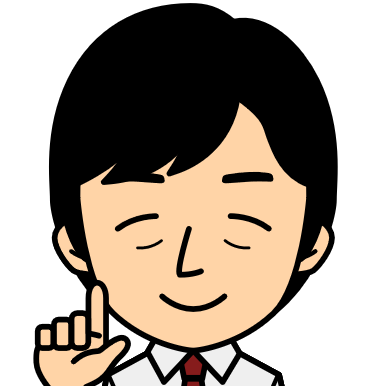
せっかく計算力があっても、文章を正しく読み取って式を立てる力がなければ、力を発揮できません。
また、近年の入試において、理科・社会の問題文はどんどん長文化しています。
内容理解よりも「問題文を読み解く」ことに時間を取られてしまうと、本来の知識や実力を出し切る前に時間切れになってしまいます。
国語力を伸ばす近道は「読書」
では、どうすれば国語力がつくのか?
結論から言うと、一番の近道は読書です。
ジャンルは問いません。自分が好きな分野であれば、何でも構いません。
活字があれば、雑誌でもOKです。
実は、私も小5までは国語が大嫌いでした。
教科書の物語は真面目すぎて、読む気がしなかったのです。
そんな私を見かねて、当時の担任の先生がこう言ってくれました。
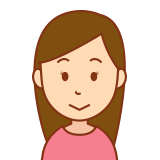
国語の教科書はマジメな文章ばかりでつまんないでしょ?
あなたは野球が好きだから、野球雑誌やスポーツ新聞を読んだらどう?
いざ読み始めると、興味のある内容なので夢中で読めました。
そのうちに漢字も自然に覚え、プロ野球チームの所在地をきっかけに、日本地理にも興味を持つようになりました。

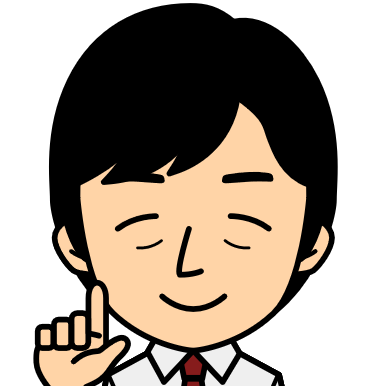
好きな内容だからこそ、「この漢字はなんて読むんだろう?」と自分から知りたくなるんですね。教科書やドリルよりも、ずっと速く覚えられたように思います。
そして中学生のとき、星新一さんの作品に出会いました。
(英語の教科書に、星新一さんの作品が掲載されていました)
ショート・ショートというジャンルの作品で、展開が速く、起承転結が明確で、とにかく面白い。
最初に読んだ「きまぐれロボット」には、衝撃を受けました。
この出会いがきっかけで読書量が一気に増え、読むスピードも上がり、気がつけば中3の頃には国語が一番得意な科目になっていました。
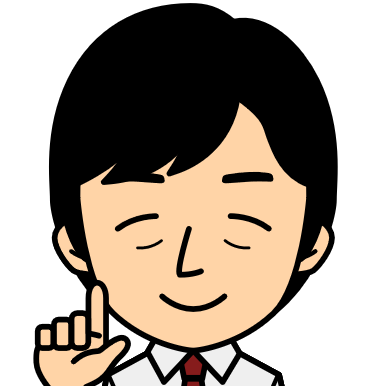
他にも、北杜夫さん、O・ヘンリーさん、阿刀田高さん、宮本輝さん、松本清張さんなど、短編集を中心に読み漁りました。
「好きなこと」から国語力は育つ
国語が嫌いな子が、教科書だけで国語を好きになるのは難しいものです。
ですから、お子様が興味を持っている分野から入ることが大切です。
たとえば——
数学が好きなAさんは、数学の文章題を通して国語力を伸ばしました。
歴史が好きなB君は、歴史小説を読むことで国語力を高めました。
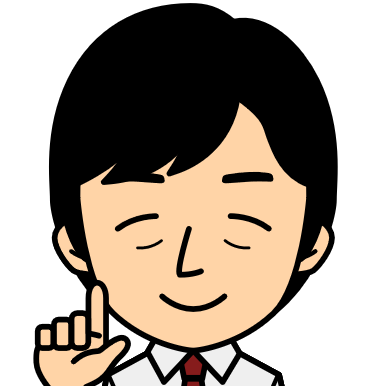
ちなみに、私の子供達は「名探偵コナンの小説版」や「読みやすい推理小説」を通じて、国語力をつけました。
読書量の多い子は、国語の点が高い
実感として、国語の成績が高い子は読書量が多いです。
しかも、国語の勉強をあまりしていなくても、テストで高得点を取ってきます。
入試や模試など、初見の文章ほど強いのが特徴です。
たとえば、当塾でも国語の科目順位で学年1位を取っている生徒がいます。
2 好きな作家さんの作品は、全巻読破するほど夢中になっていました
このように、読書量の多い生徒ほど文章の展開をつかむのが早く、読解問題に対しても“読む体力”と“集中力”が備わっています。
国語の力は勉強ではなく、日々の読書習慣の積み重ねで育っているのです。
国語力は、一生ものの武器
日本で生活していくうえで、国語ができて損することはありません。
社会人になってからも、上司からの指示を正確に読み取り、報告書や企画書を書く力として生きてきます。
企画書の内容が同僚より分かりやすければ、出世や昇給にもつながるかもしれません(笑)。
まさに新井紀子さんの言う通り——
「国語力は人生を左右する」 のです。
まとめ
国語力は、家を建てるときの「基礎工事」のようなものです。
地中の見えない部分がしっかりしていれば、どんな家もぐらつきません。

料理で言えば「だし」。
目立ちませんが、全ての味を支えます。
メイクで言えば「素肌」。
お肌の調子が良いと、メイクも綺麗に仕上がります。
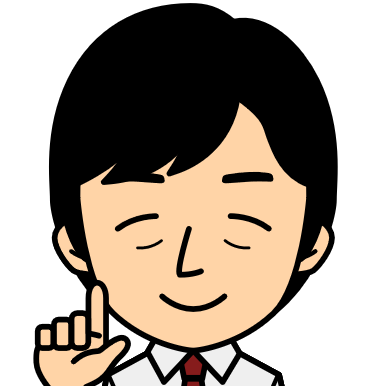
派手さはありませんが、学力を支える最も重要な部分――
それが国語力です。